いろんな価値観、先入観から解放することによっていろんなものが見えてくる、芸術の白紙還元、ということなのだそうです。
先生に紹介いただいた作品の一部を記しておきます。題名をクリックしてください。リンクで画像が見られます。
シュルレアリスムの作品を楽しみましょう!
マックス・エルンスト Max Ernst
《二人の子供は小夜鳴き鳥に脅かされ》1924 MOMAニューヨーク近代美術館
ドアを開けてみたい感じ、ベルを押してみたい感じがします。
《森と鳩》1927 テートモダン
鳩が鳥かごで守られています。
アルベルト・ジャコメッティ Alberto Giacometti
《シュールレアリストのテーブル》1933 ポンピドーセンター
ダリ Salvador Dali
《記憶の固執》1931 MOMA ニューヨーク近代美術館
精神的錯乱を故意に導入しています。
《スペイン》1938 ボイマンス美術館
二つの絵が見えてきます。
スペイン内乱の時代です。
《イメージが消える》1938 Dali Theatre museum
これも二つの絵が見えてきます。
一つはみんなが知っている「あの画家」の「あの絵」です。
マグリット René Magritte
《恋人たち》1928 MOMA ニューヨーク近代美術館
《人間の条件》1933 ワシントン、ナショナルギャラリー
私たちには思い込みがあります。
《赤いモデルⅢ》1937 ボイマンス・ヴァン・ベーニンゲン美術館
靴を履く習慣に潜む野蛮さ
マン・レイ Man Ray
《アングルのバイオリン》 1924 ゲティ美術館
「アングルのバイオリン」という言葉がフランス語にあるそうです。
画家のアングルがとてもバイオリンが上手だったことから「本格的な趣味」という意味になったのだそうです。写真からアングルの絵画も思い起こされます。
そのほかのマン・レイの素敵な写真や絵はこちら。
https://www.wikiart.org/en/man-ray
https://www.wikiart.org/ にいろいろ画像があるのを発見しました。英語で名前を入れてみてください。画像は膨大ですが、スタイル別でも見られます。
今回のレジュメですが、作家 作品名の入った新しい原稿を先生にお願いし入手しています。準備しまして、8月3日 ポンペイの講座 で配布の予定です。
中村先生、12回の講座、ありがとうございました。
<この講座を美術が大好きなお知り合いの方にどうぞご紹介ください。>
下の共有ボタンが便利です。>





.jpg)









_013.jpg)
_-_My_Dream.jpg)





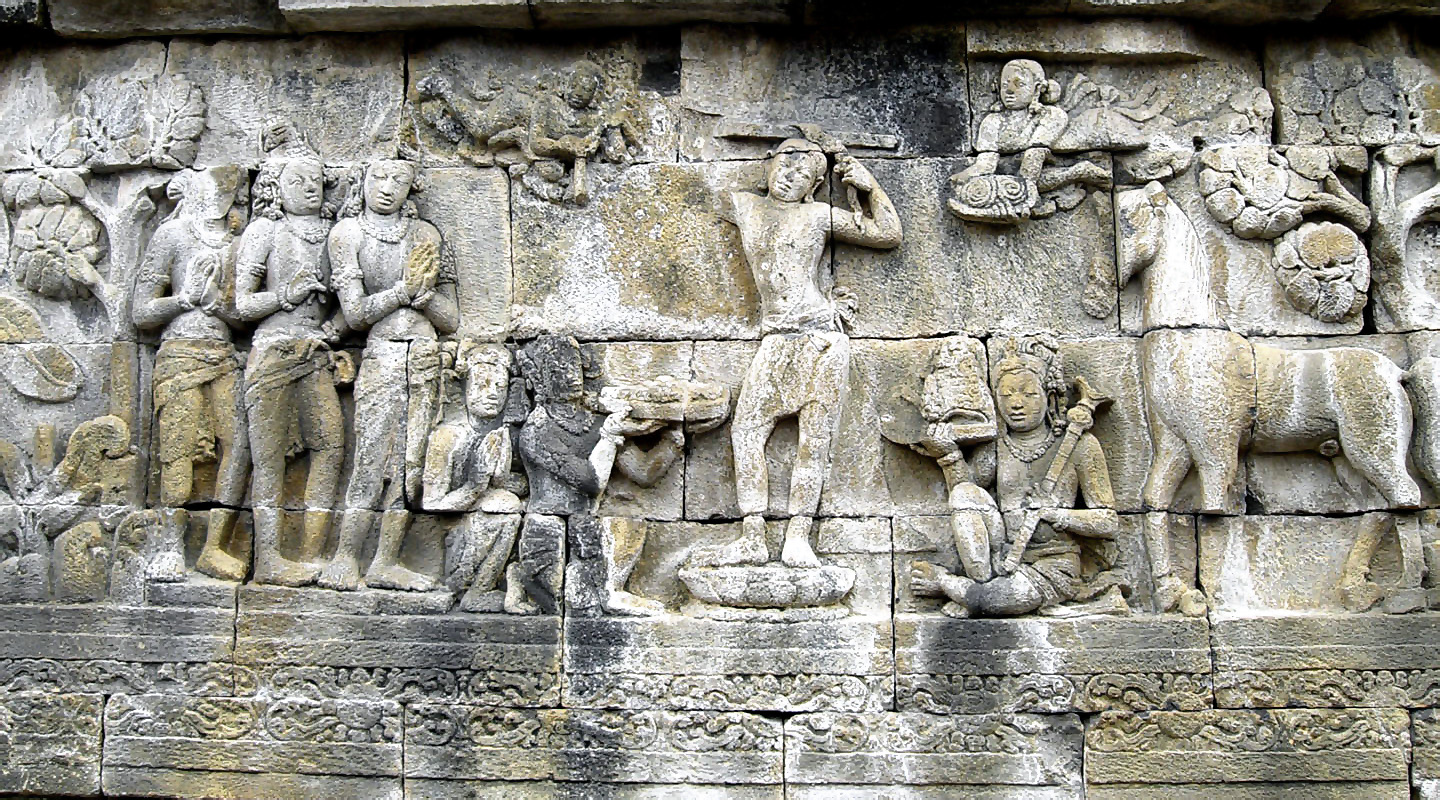





.jpg)


















